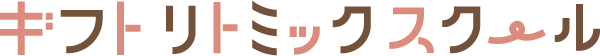—叱る前にできること、続けられるコツ、そして頼れる窓口—
「いつもの順番じゃないと動けない」「同じ服じゃないと不安」「道のこの線は絶対踏まない」——。
発達障害のある子どもに見られやすい“こだわり行動”。大人からは“融通が利かない”“わがまま”に見えがちですが、多くの場合は不安を和らげるための自己調整や、感覚の過敏・鈍麻を背景にした「困りごとのサイン」です。叱ってやめさせるより、安心を増やして回り道するほうが結果的に生活は楽になります。
ここでは、今日からできる実践ステップをまとめました。最後に、より個別の相談ができる「まい先生のこそだて相談室」もご案内します。

1. まず理解する:こだわりは“悪”ではない
こだわりは、悪いものではありません。子どもにとっては、世界をわかりやすくしたり、不安を小さくしたりするための大切なやり方です。まずは「やめさせる」より、「どう付き合えば楽になるか」を一緒に考えていきましょう。
- ”こだわり”の役割:予測不能な世界に“見通し”をつくる、感覚刺激を調整する、成功体験を積む等。
- やめさせるだけの介入は逆効果:急な禁止は不安を跳ね上げ、パニックや二次的な問題行動を招くことがあります。
- 優先順位を決める:危険・健康・学習/生活に大きな支障がある場合のみ、介入の優先度を上げる。それ以外は“付き合い方”を整える。

2. ABCで観察する:行動の前後を見てみよう
ABC分析は、行動を「前」と「中」と「後ろ」の3つで見る、とても簡単な考え方です。
- A(きっかけ):起こる前にあったこと(音・匂い・服の感触・急かし など)
- B(行動):そのときに見られた行動や表情、ことば
- C(その後):そのあと周りで起きたことや、子どもが落ち着いたきっかけ
たとえば、出発前に靴下の縫い目が当たって(A)、玄関で固まってしまい(B)、別の靴下に替えたら動けた(C)——という具合に、専門用語は使わず短く書くだけでOKです。
やり方はシンプル。A→B→Cの順で、まずは2〜3日メモしてみましょう。
行動そのものを責めるより、A(きっかけ)を減らす・C(その後)を整えるほうが効果的です。
【A(きっかけ)→ B(行動)→ C(結果)】のメモを数日取ります。
例)
- A:靴下の縫い目が当たる/出発を急かされた
- B:靴下を脱ぎ捨てる、玄関で固まる
- C:別の靴下に替えた、出発が遅れた
見えてくること:感覚要因(縫い目が当たって不快)、時間の見通し不足、言葉の指示だけでは処理しづらい等。
→ 平らな縫い目の靴下に変える+タイマーで予告する といった工夫が考えられそうです。
行動そのものを責めるより、A(きっかけ)を減らす・C(その後)を整えるほうが効果的です。

3. 今日から使える“こだわり”と上手に付き合う技
(1)見通しを“可視化”する
- 写真スケジュール/絵カード/タイムタイマーで「何を・いつまでに・次は何か」を明確に。
- 朝の支度は「①顔を洗う→②ごはん→③歯みがき→④靴」など3〜5工程に絞って掲示。

どんな子にとってもこういうのがあるとわかりやすいですよね。

右が普通の時計になっている「時っ感タイマー」。ネットで買えます!
(2)“同じ”を確保してから、少しずつ広げる
- 服や食べ物のこだわりは、“同じメーカー・素材”で色だけ変えるなど“安全基地”を残して段階的に広げていく。
- 例:白→薄いグレー→淡い色…の順で“1つだけ変える”。
(3)条件交渉は“IF-THEN(もし~なら~)”で短く
- 「もし今日は青い服がいいなら、ズボンはママが選ぶね」
- 選択肢は最大2つ。選ぶ経験が自己決定感を育て、不安を下げます。
(4)感覚に寄り添う環境調整
- 衣類:縫い目はフラットなもの・タグ無し・綿多めを選ぶ。
- 音:通学路や店の混む時間を避ける、耳栓・イヤーマフを活用する。
- 照明:蛍光灯が眩しい場合は間接照明や帽子のツバを利用する。
- 触覚:手持ちの“モフモフ”なものやスクイーズやプッシュポップなどの感触のよいおもちゃ等で安心のスイッチを用意。

(5)切り替えは“儀式化”する
- 終了の合図を毎回同じに。「タイマーが鳴ったら”おしまい”のジェスチャー→次のカードをめくる」。
- 先に次の楽しみを提示:「タイマー鳴ったら、おやつカードだよ」。
(6)“できた”を集める強化法
- 行動を細かく刻む(靴下に足を入れた/踵まで引き上げた)。
- できた瞬間に具体的に称賛:「踵を自分で引っ張れたね!」
- 「できた!」のちょっとしたご褒美やシールは小さく頻回に。ゴールは1〜3日で達成できる設定に。
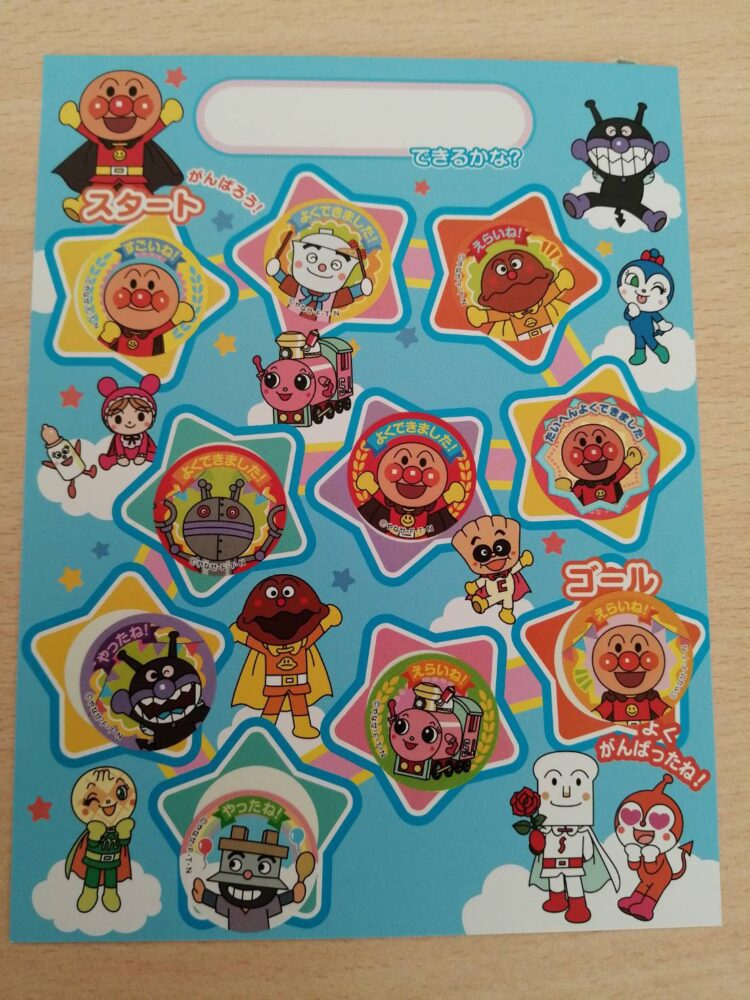
4. NGになりがちな対応と、言い換えフレーズ
忙しいときほど、つい強い言葉になってしまいますよね。大丈夫、言い方をほんの少し整えるだけで、子どもは動きやすくなります。ここでは「ダメ!」を減らして、「どうすればできる」に近づく声かけをご紹介します。
| NG対応 | よくある言葉 | 言い換え例 |
|---|---|---|
| 急な方針転換 | 「もうやめて!」 | 「あと3回でおしまい。タイマーが鳴ったら次へね」 |
| 抽象的な叱責 | 「ちゃんとして」 | 「靴下はつま先を持って、踵まで引っ張ろう」 |
| 比較・否定 | 「弟はできるよ」 | 「昨日より5分早く座れたね」 |
| 全面禁止 | 「その話はしない!」 | 「このカードの間は電車の話OK。鳴ったら次はごはん」 |

5. うまくいかないときの“テコ入れポイント”
- 頻度・時間・強度が増している → 介入が速すぎる/難易度が高すぎる可能性があります。半歩戻す、さらにスモールステップにする必要があるかもしれません。
- 睡眠・便通・食事の乱れ → これらの乱れは感覚過敏やイライラを増幅させます。生活リズムを先に整えることを優先しましょう。
- 大人の一貫性が揺れている → 家・園/学校で合意した共通ルールを作って共有する。簡単なメモでもいいので、共通ルールを可視化し、家族間や園/学校に伝えてやり取りすると効果的。
6. 困りごと別・ミニ処方箋
衣類のこだわり
- 同じメーカーの同型を複数色でローテーション。
- 新しい服は家の中で短時間→外出の順で慣らす。
ルート・順番のこだわり
- マップにAルート・Bルートの“2択”を常備。変更日は前日夜に予告し、成功したらシールで可視化。
話題のこだわり(延々と同じ話)
- 時間枠化:「電車タイムは5分」。終わりの合図後は次の活動カードへ。
- “教える係”に任命して、予定の確認やルール説明など、役割につなげる。

7. 緊急時(メルトダウン)の対応
メルトダウンとは、強い不安や疲れ、刺激が重なって心と体のコントロールが一時的に難しくなる状態のこと。泣く・叫ぶ・その場に固まる・物を投げるなどの形で表れます。わざとではありません。対応の基本は、安全を確保し、刺激を減らし、言葉を少なくして見守ることです。
メルトダウンは「困らせたいから」ではなく、助けてのサインです。コップから水があふれるように、限界を超えてしまっただけ。まずは危ない物を遠ざけ、静かな場所へ。声かけは「水のむ?」「一緒に深呼吸しよう」など短い言葉で十分です。
- 安全確保:物理的に危険な物を遠ざける。
- 刺激を減らす:人混みから離れる、光と音を落とす。
- 言葉を減らす:短いフレーズと身振り。「深呼吸」「水のむ?」
- 回復を待つ:落ち着いたあとに振り返りカード(共感「しんどかったね」/きっかけ/次の作戦)で短く整理。

8. 家族が疲れてしまわないために
毎日がんばっていると、気づかないうちに家族の電池が切れかけてしまいます。大切なのは「完璧にやる」ことより、続けられる形で休むしくみを用意すること。小さな手抜き・小さな分担・小さなごほうびで、生活の“息継ぎ”をつくっていきましょう。
- 100点を目指さない:7割で回る仕組みづくり。
- “できた”を大人も記録:小さな成功は家族の燃料。
- 外部とつながる:家と園/学校で同じ言い方・同じ合図を共有すると、一気に楽になります。簡単なメモを1枚つくるといいですね。
共有メモの例
【お子さんの得意】図鑑/電車の名前 【苦手】急な予定変更
【落ち着く合図】タイマー→”おしまい”のジェスチャー→次のカード
【やってほしい支援】始める前に写真カード/終わりはタイマー
【NG】「早く!」「なんでできないの」などの急かし

9. もっと楽になるために:専門家と“あなたの子仕様”にカスタムしよう
ここまでの工夫だけでもラクになりますが、子どもの特性・家庭の事情・園や学校の環境で最適解は変わります。行動観察の視点や、カード類の作り方、園や学校への伝え方まで伴走してくれる専門家がいると前進が早いです。
▶ まい先生の「こそだて相談室」へ
- お子さんの“こだわり行動”を叱らずにラクにする具体策を、家庭と学校/園の両面から一緒に設計します。
- 「どこから手を付ければいい?」という段階でも大丈夫。今の生活にフィットする半歩ずつを一緒に見つけましょう。
ご興味があれば、【まい先生のこそだて相談室】へお気軽にご連絡ください。
現在のお困りごと(場面・時間帯・困る理由)を3つだけメモしていただけると、初回の時間がより有効に使えます。

——
お子さんの“こだわり”は、世界を生き抜くための道具でもあります。上手に使えるように手入れしつつ、負担が大きい部分はやさしく整えていきましょう。あなたの毎日が、少しでも軽くなりますように。